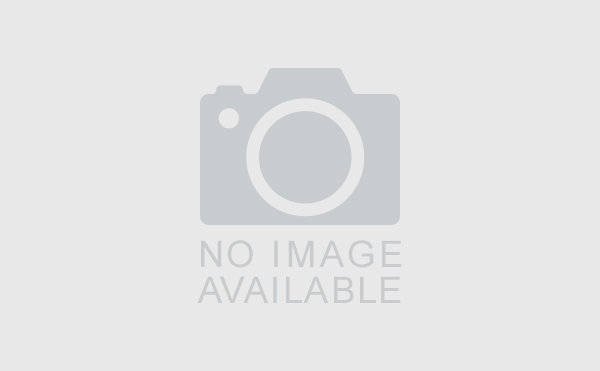【BCP 防災 コラム】大規模災害における災害関連死
・6月20日、石川県内の3つの自治体は、能登半島地震のあとに亡くなった9人について災害関連死と認定しました。これによって能登半島地震の災害関連死は、388人となり、直接死も含めた死者は616人になったとのことです。
・災害関連死は、災害による直接的な死亡ではなく、避難生活のストレスや持病をもたれている方が適切な医療サービスを受けられないことなどにより間接的要因で死亡するものです。内閣府防災担当は災害関連死を以下のように定義しています。
「災害関連死:当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づき災害が原因で死亡したものと認められたもの」
・先般3月に政府より公表された南海トラフ巨大地震被害想定では、初めて災害関連死者数が試算されましたが、その数は最大で5万2000名に上ります(いわゆる直接の死者数は最大29万8千人、避難者は1週間後最大1230万人)。
・社員等人材は会社にとって最も大切な財産です。南海トラフ巨大地震や首都直下地震においては多くの避難者が発生し自社の社員・ご家族様も避難者となる可能性があるわけですが、避難生活が長引くとストレスがかかるなどして災害関連死のリスクが高まります。
・直接死と異なり、会社の対策本部が機能できれば、避難されている自社の社員及びご家族様に対し会社、組織として何かできることがあるかもしれません。人道的観点に加えて組織の人的戦力維持の観点からも、震災後に健康に職場に来ていただくことは必須といえるでしょう。災害対応計画、BCPなどに含めて平素からそのような体制を構築しておくことをお勧めします。(了)