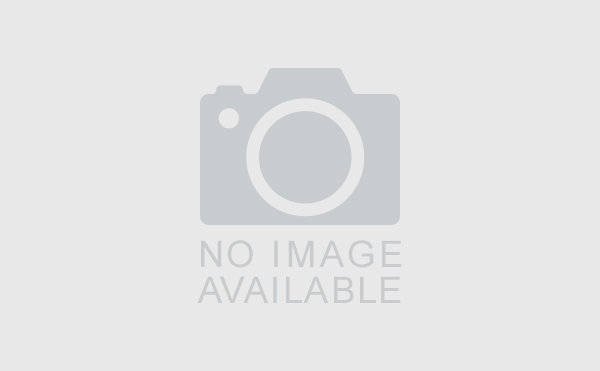【防災 BCP コラム】南海トラフ巨大地震への備え、“南海トラフ地震臨時情報”とは?
防災コンサルタントが簡単に解説、”臨時情報”で事前避難の必要あり?
・先般、8月20日(水)、読売新聞から、南海トラフ地震臨時情報のうち最も切迫性が高い「巨大地震警戒」が出た際、津波に備え、自治体が1週間の事前避難を求める住民が全国で計52万人超(2日後の22日、内閣府から人数の訂正があり、“約51万6000人”とのことです。)に上る旨の記事が報道されました。昨年8月、九州沖地震により気象庁から南海トラフ地震臨時情報のうち「巨大地震警戒」より一段低い「巨大地震注意」が発出されましたが、広範な地域で自粛ムードも広がり海水浴場はガラガラにだったことも思い起こされます。ここではについて解説します。
“南海トラフ地震臨時情報”のながれ。
“南海トラフ地震臨時情報”とは、南海トラフ沿いで異常な現象を観測された場合や地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合等に、気象庁から発表される情報です(内閣府)。
気象庁において、マグニチュード6.8以上の地震、通常と異なるなるゆっくりすべり等の異常な現象を観測した後、5~30分後に南海トラフ地震臨時情報(調査中)が発表されます。この段階ではあくまで“調査中”です。
南海トラフ地震臨時情報(調査中)発表後、「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の臨時会合などが開催され異常現象を評価します。約2時間以上かけて検討・評価し“巨大地震警戒”(最も重い)、“巨大地震注意”(“警戒”に次いで重い)そして“調査終了”のいずれかを判定し、発表します。
・“巨大地震警戒”(最も重い)、“巨大地震注意”が発出された場合は、自治体が、津波避難が間に合わない地域の住民に対し少なくとも1週間の事前避難を求めます。とくに配慮が必要な高齢者や障害者の方々は避難が求められます。
“巨大地震警戒”、“巨大地震注意”で事前避難、ただしその前に避難も。
・“南海トラフ地震臨時情報”に基づく行動は、マグニチュード6.8以上の地震から早くて5分+2時間で警戒などが発表されて、そののち行動、という流れになりますが、そもそもマグニチュード6.8以上の地震を感じた段階で津波を予期し、“南海トラフ地震臨時情報”を待たずに直ちに行動をとる必要がある場合もあることに注意してください。特に内閣府が指定している津波特別対策地域は30分以内に30cm以上の津波が到達、とされていますので大変危険です。揺れを感じたら(振れが収まって安全を確保したら)、すぐ行動でしょう。
・また、“巨大地震警戒”、“巨大地震注意”が発出されたら“1週間の事前避難”旨の報道も見られましたが、“少なくも1週間”です。7月に発生したカムチャツカ半島沖の地震では、7月20日にマグニチュード(M)7級の地震があり、その10日後にM8.8の大地震が発生しました。あくまで目安と認識してください。
本当に避難するの? 基本的には避難してください。
・昨年8月の“巨大地震注意”では、実際に避難しない場合でも海岸付近での行動を避ける、西日本の太平洋に面する都市への移動を避ける、など多くの行動が自粛されました。これにより経済活動も大きな影響を受けました。国は今回の計52万人超(2日後の22日、内閣府から人数の訂正があり、“約51万6000人”とのことです。)という調査結果を踏まえ、事前避難が円滑に行われるよう自治体への助言・支援を進めるとのことです。
・昨年もそうでしたが、自治体も何をどの様に勧告等すればよいのか頭を悩ますでしょう。現時点では避難に伴う経済補償などの制度はありません。今後、国と自治体とが一体となってガイドライン的なものが明らかになると思いますが、少なくとも、注意がでたら、津波特別対策地域にはいかない、津波特別対策地域の方々の要配慮者は実際に避難する、要配慮者でない方も30分以内に高台に避難できない場所で生活する場合は避難する、避難しない場合においても完璧に避難の準備をする、すぐに避難できるように行動を制限する、などの行動が必要だと思料します。(了)