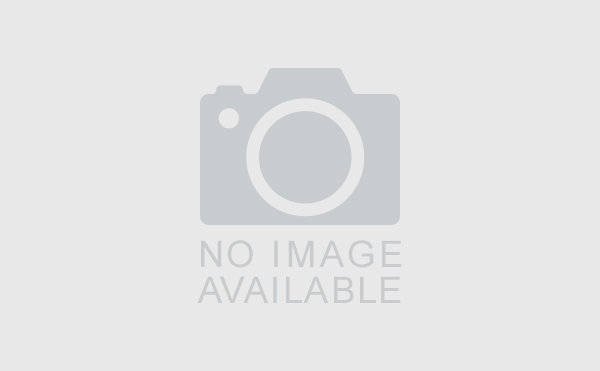【防災 災害対応 BCP コラム】津波からの避難 南海トラフ地震の災害対策
前の防災コラムにおいて南海トラフ地震の津波被害について簡単に説明させていただきましたが、この記事では、津波からの避難について説明します。
あっという間にやってくる津波 逃げる時間がないときは“垂直避難”を!
・南海トラフ地震の震源域は、先般発生したカムチャッカ半島地震などに比して、陸から非常に近いといえます。恐ろしいほどの波高で津波がアッとゆう間にやってくる可能性が高いといえます。
・一般的に日本では海に面した沿岸部に市街地が発達している場合が多いですが、逃げる時間があまりないことを踏まえて、大きな揺れを感じたらまずは自分がいる建物、または近くのビルなどの高層に逃げるようにしましょう。特に内閣府の津波特定指定地域(30cm以上の津波が30分以内に到達する可能性がある地域。千葉県の房総半島から宮崎県までの広範な地域が指定されています。)では、市中のオフィスビルなどが津波避難場所として指定されている場合が多いです。自分の普段の行動範囲のなかでどこが避難場所になるのか事前に確認しましょう。
・無事にビルなどの建物に避難し、津波をやり過ごすことができたとしても付近一帯が冠水し移動できない、といった状況が多々発生すると思います。そういった場合は基本的に救助を待つことになりますが、ビルに入居する企業などは備蓄食料、ラジオ、携帯で電源などに加えて自衛隊、消防、警察などの救助者に対して“要救助”などと表示したサインボードなどコミュニケーションがとれるような装備を準備しておくとよいでしょう。
50㎝の水深で浮く! 車両での避難は慎重に。
・遠くに避難する場合、車両での移動も選択肢の一つになり得ると思いますが慎重に判断しましょう。先般のカムチャッカ半島地震に伴う津波では、警報・注意報発令から津波の到達予想時間まで時間の余裕があったこともあり自動車で避難する方も多々おられましたが、諸所渋滞が発生したそうです。現状、津波などからの避難ついて直接的に車両移動を統制するシステムはなく、都道府県の地方自治体警察がマニュアルで警官を配置して統制、ラジオ等で渋滞情報を入手して自ら回避、といったことがせいぜいだと思います。発災(揺れ)直後の大切な時間帯は空白時間となるでしょう。(将来的はAI活用により、人の判断を介することなく自動的に交通を統制しかつ伝達するシステムができるかもしれません。)
・南海トラフ地震においては、津波の到達予想時間が極めて早いこと、揺れも甚大であることなどから、警察やラジオ、テレビ局などが発災直後(津波からの避難時間30分から1時間)にフルで機能する保障はありません。皆が車両で避難した場合、人口過疎地など一部を除いて、ほぼ確実に渋滞が発生するといえるでしょう。
・乗用車であれば水深50㎝で浮くといわれています。多くの車両のような重量物が想できない水流に乗って浮遊し向かってくる状況は考えただけでも恐怖です。
・南海トラフ地震で津波被害が予想される地域における車両での避難は、避難者及び他者にとってリスクが高いといえます。車両での避難は慎重に判断しましょう。(了)